御稲御倉(みしねのみくら)は 神宮神田から収穫した抜穂(ぬいぼ)〈三節祭で大御饌(おおみけ)として神前にお供えされる〉御稲が納められます 祭神は御倉の守護神とされ 皇大神宮(内宮)の所管社です その少し北側には かつて天皇以外のものから奉られた幣帛も納めた外幣殿(げへいでん)があります

Please do not reproduce without prior permission.
目次
1.ご紹介(Introduction)
この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します
【神社名(Shrine name)】
御稲御倉(Mishine no mikura)
【通称名(Common name)】
【鎮座地 (Location) 】
三重県伊勢市宇治舘町(内宮境内)
【地 図 (Google Map)】
【御祭神 (God's name to pray)】
《主》御稲御倉神(みしねのみくらのかみ)
【御神徳 (God's great power)】(ご利益)
【格 式 (Rules of dignity) 】
・〈皇大神宮(内宮)所管社〉
【創 建 (Beginning of history)】
『神宮綜覧』〈1915年〉に記される内容
【抜粋意訳】
三十、外幣殿(ゲヘイデン)
板垣の外、乾の角にあり。本殿は、古は皇后宮幷に皇太子よりの幣帛、及び諸國神戸の調(みつぎ)の荷前(のざき)等を納め奉る殿舎なりしが、後には古神實幣帛を納むることとなり、現今も猶ほ古神實の類を納め奉る。
之を外幣殿と云ふは、内院の寶殿に対して、此は外院にある幣殿の義なるべし。
さればその構造も、東西實殿と同じ狀なりしを、後世に至うて変轉し。又其の位置も数数変遷したれども、慶安二年に、西御敷地の西南に再興せられたるを、明治二十二年の御遷宮に方り、舊記を考覈して、現今の地に移轉せられたり。三十一、御稲御倉神(ゴタウノミクラ)
外幣殿の南にあり。御稻御倉とは、御常供田より苅取りし御稻を納むる所なり。往古は調御倉(ツキノミクラ)・鹽御倉(シホノミクラ)〔・又 御器御倉(ゴキノミクラ)と云ふ〕舗設御倉(フセツノミクラ)と合わせて四宇ありて、内外の玉垣の間に、西の宮地にては東面に、東の宮地にては西面に建てられしが、後、他の三宇は廃絶して御稻御倉のみ存せしを、明治二十二年の御遷宮に方り、現今の地に移されたり。
〇御稲御倉神(ミイネノミクラノカミ) 壹座 御稻御倉の守護神として、奉齋せる神霊なるを以て、別に神殿を構へずして、御倉の中鎮座す。
【原文参照】
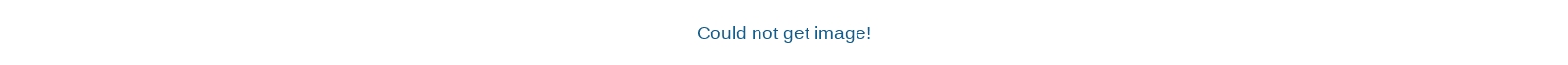
神宮司庁 編纂『神宮綜覧』,国史研究会,1915.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1907594
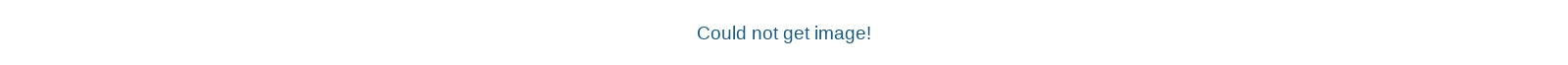
神宮司庁 編纂『神宮綜覧』,国史研究会,1915.10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1907594
【由 緒 (History)】
『神宮摂末社巡拝』下〈昭和18年〉に記される内容
【抜粋意訳】
御稲御倉神(みいねみくらのかみ)
御正殿を退下して、元の参道を戻り、忌火屋殿の東の岐れ道を北へ折れて登ると、忌火屋殿の東側に當って、御稻御倉(ごたうのみくら)一殿あり。東面で、御金物の御飾りのない殿舎である。御神田から苅取りつて來た御稻を納めて置く所である。皇大神宮の由貴祭(ゆきさい)のときには、この御殿より御稻を下ろし奉り、御饌として供進し奉るのである。御稻御倉神は、この御倉の守り神として、本殿の中に鎭祭されてゐる。御祭神は御稻神 倉稻魂神(うがのみたまのかみ)である。皇大神宮所管社の一つである。
外幣殿(げへいでん)
御稻御倉の地隣りで、南面してゐる殿舎が外幣殿である。この殿舎には御金物が打ってある。共にその御前まで進みて拜することが出來るので、神明造(しんめいづくり)の構造を眼の邊りに充分拜することが出來る。瑞垣内の東實殿を内の幣帛殿とするならば、これは、外の幣帛殿に當るものである。延曆儀式帳の定むる所に從ふと、皇后、皇太子並に東海道驛使の幣帛、及び神戸(かんべ)の調(みつぎ)の荷前(のさき)等を納め、又古神實、幣帛等を納めることになってゐるが、現在は、古神費の類を納むる所となってゐる。
【原文参照】
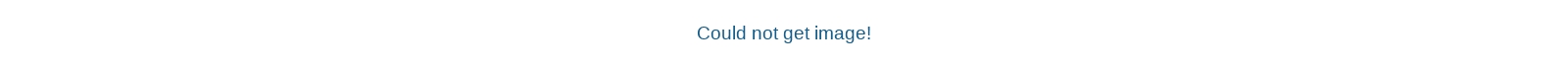
猿田彦神社講本部 [編]『神宮摂末社巡拝』下,猿田彦神社講本部,昭和18. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1033626
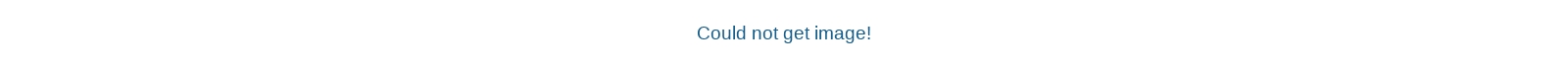
猿田彦神社講本部 [編]『神宮摂末社巡拝』下,猿田彦神社講本部,昭和18. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1033626
【神社の境内 (Precincts of the shrine)】
御稲御倉は 皇大神宮(内宮)の所管社です
・皇大神宮(内宮)
【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】
スポンサーリンク
この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)
この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています
『延暦儀式帳(えんりゃくぎしきちょう)』について
延暦儀式帳(えんりゃくぎしきちょう)は 伊勢神宮の皇大神宮(内宮)に関する儀式書『皇太神宮儀式帳』(こうたいじんぐうぎしきちょう)と豊受大神宮(外宮)に関する儀式書『止由気宮儀式帳』(とゆけぐうぎしきちょう)を総称したもの
平安時代成立 現存する伊勢神宮関係の記録としては最古のものです
両書は伊勢神宮を篤く崇敬していた桓武天皇の命により編纂が開始され
両社の禰宜や大内人らによって執筆されました
皇大神宮と豊受大神宮から 神祇官を経由して太政官に提出されて
延暦23年(804)に成立しました
『皇太神宮儀式帳(こうたいじんぐうぎしきちょう)』〈延暦23年(804)〉の「太宮壹院」に記される内容
゛幣殿一院゛とは
ここに載る゛幣殿一院゛とは
現在の外幣殿(げへいでん)〈かつて天皇以外のものから奉られた幣帛も納めた殿〉に相当するものと考えられます
゛幣殿一院
殿一宇 長一丈五尺 弘一丈二尺 高八尺
玉垣一重 廻長丗八丈゛
゛御倉一院゛とは
ここに載る゛御倉一院 倉四宇゛とは
板垣外の西方に古代より建てられていた4棟1組の御倉「調御倉(つきのみくら)・御塩御倉(みしをのみくら)・鋪設御倉(しつらいのみくら)・御稲御倉(みしねのみくら)」と考えられている
・調御倉(つきのみくら)は 味噌の御倉
・御塩御倉(みしをのみくら)は 鹽の御倉
・鋪設御倉(しつらいのみくら)は 調度の品の御倉
・御稲御倉(みしねのみくら)は 稲穂の御倉
であろうとされています
御稲御倉(みしねのみくら)は〈現 皇大神宮(内宮)所管社〉です
御塩御倉(みしをのみくら)は 現在の御塩殿神社〈皇大神宮(内宮)所管社〉で造られた鹽の御倉です
゛御倉一院
倉四宇 長各一丈八尺 弘各一丈五尺 高一丈
臥堅魚木 各四枚
玉垣 廻長丗八丈゛
゛御酒殿一院゛とは
ここに載る゛御酒殿一院゛とは
現在は 五丈殿の奥に鎮座する・御酒殿(みさかどの)・由貴御倉(ゆきのみくら)と考えられます
・御酒殿(みさかどの)は 古くはここで神酒を醸造していました
・由貴御倉(ゆきのみくら)は 古くは お供えものや果物などを納めた御倉
であろうとされています どちらも〈現 皇大神宮(内宮)所管社〉です
゛御酒殿一院
酒殿一間 長四丈 弘一丈七尺 高八尺 庇一面
務取廰一間 長三丈 弘一丈 高一丈
倉二宇 長各一丈八尺 弘各一丈五尺 高一丈盛殿一間 長五丈 廣一丈七尺 高八尺
大炊屋一間 長二丈 弘一丈 高七尺
防往籬一重 長丗四丈゛





スポンサーリンク
【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)
あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します
御倉(みくら)・神社(じんじゃ)神明造(しんめいづくり)の建築様式について
現在では
・御倉(みくら)は゛寺社の貴重物を納める倉(くら)゛
・神社(じんじゃ)は゛神を祀る社(やしろ)゛として考えられています
しかし 御倉と神社の両方の建築様式から捉えると
どちらも弥生時代から広範囲に広まったとされる゛水田稲作゛で収穫された稲穂を納めた゛高床式の「倉」゛の建築様式です
日本では 弥生時代頃に倉庫として使われたのがはじめで 穀物を湿気対策やネズミ等の害から守るために用いられていたとされています
神社建築様式の1つ神明造は この様式から発展したとされます
登呂遺跡〈水田遺構を伴う弥生時代の集落遺跡〉の高床式

Please do not reproduce without prior permission.
弥生時代に 人々の生活を守る神として 稲〈御米〉が祀られていた例は各地に残っています
中でも 対馬の赤米神事は現代まで継承されています
赤米の頭受け神事(アカゴメノトウウケジンジ)
〈豆酘の祭祀習俗の中でも 赤米を神として祀る行事として有名です この世話役(頭)の新旧交替の儀式を「頭受け」といい 毎年旧暦1月10日の深夜に多久頭魂(タクズタマ)神社にて行われて 御神体〈赤米〉が前年の頭主の家から次の頭主の家へと「神渡り」する 豊作を祈願する「受取り渡し」の儀式が行われます〉
https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/material/files/group/3/2.pdf
おそらく 伊勢の神宮゛御稲御倉(みしねのみくら)゛を所管社゛神社(かみのやしろ)゛とするのも 米そのものを神として崇めた 古代の信仰からくるものなのでしょう
スポンサーリンク
内宮・外宮の別宮・攝社・末社・所管社について
お伊勢さん125社について
スポンサーリンク
【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)
この神社にご参拝した時の様子をご紹介します
皇大神宮(内宮)の域内に鎮座します
・皇大神宮(内宮)
皇大神宮(内宮)から荒祭宮へ向かう参道の脇に 御稲御倉(みしねのみくら)があります

御稲御倉〈皇大神宮(内宮)所管社〉に参着

Please do not reproduce without prior permission.
御稲御倉(みしねのみくら)は 御正宮と同じ唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)です
御正宮は 一般には見ることができませんが 参道の脇にある御稲御倉は 小ぶりではあるものの本物の唯一神明造を目の当たりにできます
御稲御倉にすすみ お祈りをします
ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります
殿舎は 東向き
20年ごとの式年遷宮で造替られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.
御稲御倉の北には外幣殿(げへいでん)があります

Please do not reproduce without prior permission.
外幣殿(内宮境内)に参着
かつて天皇以外のものから奉られた幣帛も納めた建物
殿舎は 南向き
20年ごとの式年遷宮で造替られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.
【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)
この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します
『神宮要綱』〈昭和3年〉に記される伝承
【抜粋意訳】
皇大神宮 宮域 殿舎
外幣殿 〔神明造、萱葺、御階付〕
外幣帛殿とも稱す。古より式年造替の殿舎なり。皇太神宮儀式帳によれば、皇后・皇太子竝に東海道驛使の幣帛及び神戸の調の荷前等を納め、又は古神實・幣帛等をも收藏せしが、現今も猶古神實の類を納む。古は大宮院の外にありて玉垣にて囲まれしが、延曆以後に至り御垣中に入りて御稻御倉等と併立し、内院の殿舎となりしも、造替久しく中絶したりしに、慶安二年西御敷地の西南に再興せられ、明治二十二年更に舊記を考覈して現今の地に移轉す。現在御建物の丈尺は儀式帳に准據したり。
御稲御倉 〔神明造、萱葺、御階付〕
本殿は皇太神宮儀式帳に「御倉一院倉四宇、〔長各ー丈八尺・弘各丈五尺、高一丈〕臥に堅魚木各四枚」とありて、卽ち御稻御倉・調御倉・鹽御倉・鋪設御倉のーなり。御常供田の稻を收藏し、由貴祭に臨みこの殿舎に就きて所謂御稻奉下の行事を行ひたり。中世以後他の三宇の御倉は廃絶せしも當御倉のみ存續し、寛正頃より神嘗祭に方り、禰宜所進の織御衣(おりのみそ)を當殿に於て母良及び織女をして奉織せしむることとなり、之を御機殿とも稱したり。
明治以後御稻御倉神を鎭祭し神居の殿舎となれり。所管社御稻御倉神の條参照すべし 。皇大神宮所管社 御稲御倉神
鎭座地 皇大神宮神域御稻御倉内
右神宮司廰造替
御稻御倉神(ミイネミクラノカミ)は、御稻御倉の守護神どして奉齋せらる。古來神殿無く同じ御倉の中に鎭座あり。斯の御倉はもと御常供田の稻を收めたる所なりしが、後に禰宜奉納の御衣を此の御倉にて奉織せる故に、一に御機殿とも稱するに至れり。祭神は大治御形記に御倉神女(ミクラノカミタウメ)なり、保食神是なりとあり。又神名祕書には素蓋嗚尊の子 宇賀之御魂神、一名專女、亦白狐と號すと記し、神拜次第祕抄には、宇賀乃御魂神となせり。倉稻魂命〔宇迦之御魂神〕が伊拜諾尊の御子神に坐すことは日本紀神代卷の一書に見え、又延喜式大殿祭祝詞には屋船豊宇氣姫命也是稻霊也ともありて食物原始の御神に坐す。古事記には、此の神を以て須佐之男命の御子となせり。
【原文参照】
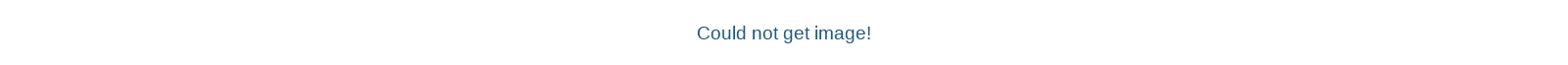
神宮司庁 編『神宮要綱』,神宮司庁,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1189814
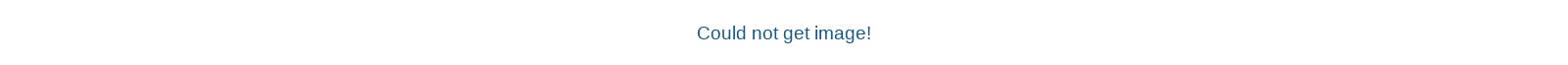
神宮司庁 編『神宮要綱』,神宮司庁,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1189814
御稲御倉〈皇大神宮(内宮)所管社〉&外幣殿(内宮境内)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.











