恵比須神社(えびすじんじゃ)は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社の一つです 本殿付近は 和文学者の平敷屋朝敏(へしきやちょうびん・1701~1734年)が 1734年に処刑された場所だと 伝わります

Please do not reproduce without prior permission.
目次
1.ご紹介(Introduction)
この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します
【神社名(Shrine name)】
恵比須神社(Ebisu shrine)
【通称名(Common name)】
【鎮座地 (Location) 】
沖縄県那覇市字安謝251
【地 図 (Google Map)】
【御祭神 (God's name to pray)】
《主》天受久女龍宮王御神(てんじゅくめりゅうぐうおうおんかみ)
またの名を 天照大御神(あまてらすおほみかみ)
【御神徳 (God's great power)】(ご利益)
【格 式 (Rules of dignity) 】
・琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の兼務社
【創 建 (Beginning of history)】
恵比須神社(那覇市安謝)は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社の一つです
【由 緒 (History)】
昔は島だったとのこと 海岸に聳える琉球石灰岩の丘
天風龍大御神(あまふうりゅうおおかみ)の御嶽あり
【神社の境内 (Precincts of the shrine)】
【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】
恵比須神社(那覇市安謝)は 琉球八社゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社です
・沖宮(那覇市奥武山町)
スポンサーリンク
この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)
この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています
安謝の処刑場跡について
恵比須神社の鳥居の右側を進むと 本殿下辺りに 琉球王府時代の安謝の処刑場跡〈琉球王府が公認した刑場〉があり 和文学者の平敷屋朝敏(へしきやちょうびん・1701~1734年)が 1734年に処刑された場所だと 伝わります
恵比須神社と琉球王府時代の処刑場跡には 特別な関係はないとのこと
゛埋立て前の海岸線が語る安謝・天久の琉球秘話゛「琉球王朝時代の処刑場」
下記に詳しい事が記されています
「琉球王朝時代の処刑場」https://hubokinawa.jp/archives/7488
スポンサーリンク
【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)
あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します
゛沖宮(那覇市奥武山町)゛の先代 宮司゛比嘉真忠(1914-1990)゛によって沖縄各地に創建された神社
いずれも御祭神は 天受久女龍宮王御神(てんじゅくめりゅうぐうおうおんかみ)を祀ります
またの名を 天照大御神(あまてらすおほみかみ)
・恵比須神社(那覇市安謝)
・恵比須神社(那覇市安謝)
・奥武山世持神社(那覇市奥武山町)

Please do not reproduce without prior permission.
・伊計神社(うるま市与那城伊計)
・伊計神社&ヌンドゥンチ(うるま市与那城伊計)
・宜名真神社(国頭村宜名真)
・神着宮(名護市字安部)
・伊平屋天巌戸神社(伊平屋村田名)
スポンサーリンク
【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)
この神社にご参拝した時の様子をご紹介します
若狭ICから海岸線を北上 約2.7km 車6分程度
昔は島だったとれる 琉球石灰岩の丘の上に鎮座します
恵比須神社(那覇市安謝)に参着

Please do not reproduce without prior permission.
鳥居の横に゛奉仕御案内゛の看板があり 赤い鳥居が建ち 階段下に一対の石獅子が座します

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.
一礼をして 鳥居をくぐり 階段を上がります
鳥居の扁額には゛恵比須神社゛とあります

Please do not reproduce without prior permission.
拝殿にすすみます
ちょうど 御祈祷をされる方が 御神職とともに拝殿に進むところでしたので
暫くして
賽銭をおさめ お祈りをします
ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.
本殿の裏手 弁財天と 天風龍大御神(あまふうりゅうおおかみ)の御嶽をお参りしました

Please do not reproduce without prior permission.
参道石段を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.
スポンサーリンク
【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)
この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します
『海南小記』 (かいなんしょうき)〈大正14年(1925)〉に記される伝承
柳田国男著 大正14年(1925)4月、大岡山書店刊
1920年に九州の東海岸から沖縄・奄美を旅行したときの紀行文と論考からなり 琉球文化の古層から日本人が北上したとする仮説を出した古典的著作
この中に 沖縄三十六歌仙の一人゛平敷屋朝敏(へしきや ちょうびん)〈1701~1734〉゛が 王府の高官を批判し 安謝港近く(恵比須神社(那覇市安謝)本殿付近に朝敏らが刑死した刑場があったとされる)にて磔刑に処せられた事が記されています
文中では 子孫は無いとしていますが 現在でもその子孫は与那国島いるとのことです
【抜粋意訳】
海南小記 一八 七度の解放
平敷屋朝敏(へしきや てうびん)、才華は在五中將の如く、生源は猶遙かに数奇であった。どこの國でも策略を以て、老いたる政治家と闘へば敗れる。彼が十四人の同志と共に安謝(あじゃ)の濱邊で斬られたのは、其三十六の歳であった。妻は官に没せられて婢と為り、孤兒は與那國(よなぐに)の島に流され、今はもう家の衰運を嘆くべき子孫も残って居らぬ。
・・・・
・・・・
【原文参照】
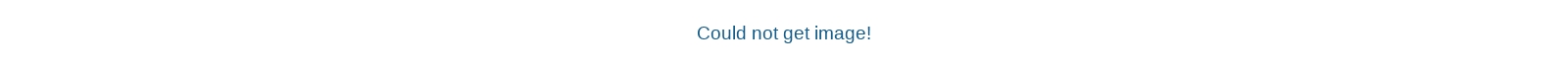
柳田国男 著『海南小記』,大岡山書店,1925 2版. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1871757
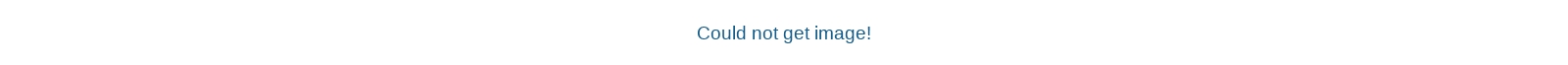
柳田国男 著『海南小記』,大岡山書店,1925 2版. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1871757
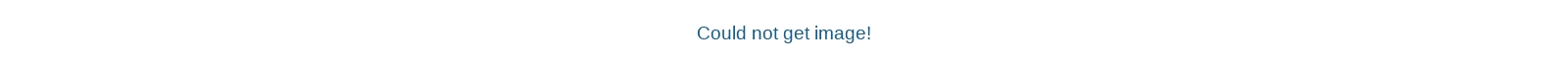
柳田国男 著『海南小記』,大岡山書店,1925 2版. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1871757
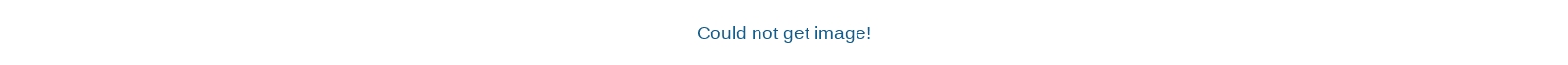
柳田国男 著『海南小記』,大岡山書店,1925 2版. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1871757
恵比須神社(那覇市安謝)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.
・沖宮(那覇市奥武山町)
恵比須神社(那覇市安謝)は 沖宮(那覇市奥武山町)の兼務社











