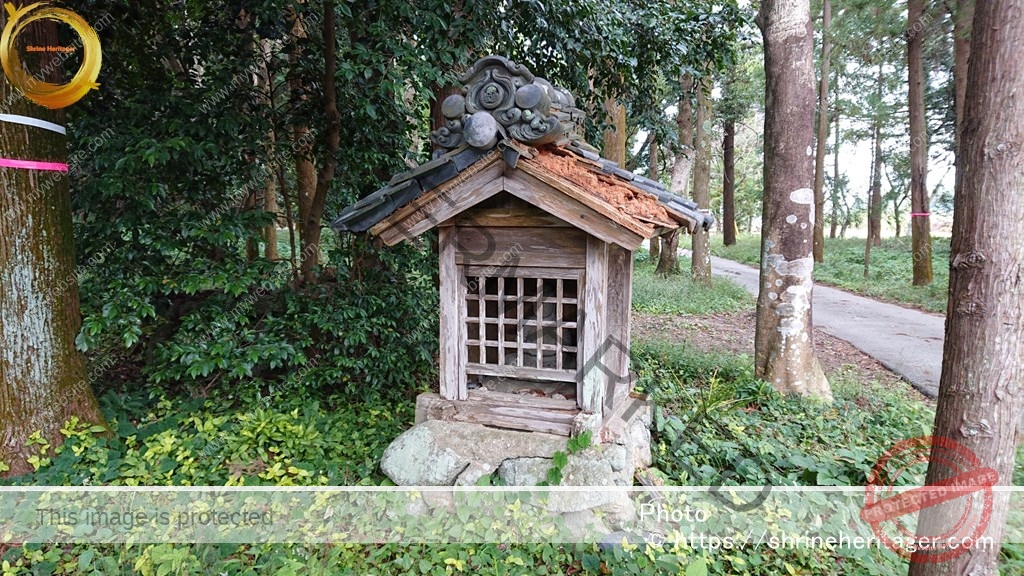延喜式神名帳
-

諏訪大神社(甲斐市宇津谷)(日本武尊が創始 延喜式内社)
諏訪大神社(すわだいじんじゃ)は 倭建命(やまとたけるのみこと)が北山・武川・逸見の賊を平定し 残党の復起せぬよう平穏を祷り 鎮護の神として倭文神 建葉槌命を祀り 良民初めて安居するを得て 初在家の名これより起ると口碑に伝わる 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)の論社です
-

倭文神社〈降宮明神〉(韮崎市穂坂町宮久保)〈延喜式内社〉
倭文神社(しずりじんじゃ)は 古代 穂坂御牧(ほさかのみまき)の役人の妻や娘などが織った精巧な織物の技芸上達を祈り祀ったのが起りとされ 山宮(柳平)の古社地より現在地へ降られた伝承と織宮(おりみや)の意から 降宮(おりみや)と呼称される 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)の論社です
-

本宮倭文神社(韮崎市穂坂町柳平)〈延喜式内社の元宮〉
本宮倭文神社(ほんぐうしずりじんじゃ)は 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)とされる倭文神社降宮明神(宮久保)の山宮であった棚機宮〈七夕社〉が 神明社(上村組)・貴船神社(窪村組)・天神社(武田の烽火台と云われる城山)と貴船神社の地に(1959)合併し 本宮倭文神社と社名を改めたものです
-

倭文神社(与謝郡与謝野町三河内)〈延喜式内社〉
倭文神社(しどりじんじゃ)は 和銅五年(712)この地で綾錦を織ることとなり 丹後國一之宮 籠神社 海部直愛志(あまべのあたいえし)が勅命を奉じて 倭文神を祀り創建した 延喜式内社 丹後國 與謝郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)とされ 貞応二年(1223)ご神託があり 筬(おさ)村から現今の石崎の社に奉遷されました
-

倭文神社(舞鶴市今田 小字津ノ上)〈延喜式内社 倭文神社〉
倭文神社(しどりじんじゃ)は 927 AD.延喜式内社 丹後國 加佐郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)とされ 創立は それより相当古くから当地に鎮座されていた云う 伝説によれば 一条天皇正暦元年(990)源頼光が大江山の鬼退治に出陣の途中 当神社に山伏の姿で武運の長久を祈願したとも伝えられています
-

倭文神社(鳥取市倭文)〈延喜式内社 倭文神社〉
倭文神社(しとりじんじゃ)は 倭文(しとり/しづり)」とも読み「しづ織り」という絹織物のことを指し 機織り(はたおり)を業(なりわい)とする倭文部の民がこの地に居住し 祖神「倭文神・建葉槌命(たけはづちのみこと)」を奉斎したと伝わる 延喜式内社 因幡國 高草郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)です
-

酒屋神社跡地(松原市三宅中)〈延喜式内社 旧鎮座地〉
酒屋神社跡地〈旧鎮座地〉(さかやじんじゃあとち)は 延喜式内社 河内国 丹比郡 酒屋神社(鍬靫)(さかやの かみのやしろ)の旧鎮座地です かつて神社の西側に酒蓋池(さかぶたいけ)が広がり 池の東北に酒屋井(さかやい)と称する井戸が存在していて その井戸から神が出現したと云う 酒屋権現(さかやごんげん)と呼ばれていた
-

屯倉神社(松原市三宅中)&〈境内合祀 延喜式内社〉酒屋神社
屯倉神社(みやけじんじゃ)は 三宅天満宮として 上古より鎮座の「穂日の社」と云う天神で 天慶五年(九四二年)菅原道眞公をお祀りしたのがその創建であると云われます 延喜式内社 酒屋神社(さかやじんじゃ)は 同じく三宅に鎮座していましたが 明治40年(1907)神社合祀政策により境内合祀社へ遷座されたものです
-

大神宮跡(京田辺市三山木東荒木)〈延喜式内社 佐牙乃神社(鍬靫) 旧跡〉
大神宮跡(京田辺市三山木東荒木)は 延喜式内社 山城國 綴喜郡 佐牙乃神社(鍬靫)(さかの かみのやしろ)の 旧跡とされ 木津川の水害の為 永享年間(1429~1441)に この地から現在の佐牙神社の鎮座地に遷座しました 今でも祭日には 神輿の渡御があり 山本宮座の太夫八人がこの地へお参りをします
-

酒屋神社(京田辺市興戸宮ノ前)〈神功皇后の持ち帰った"九山八海の石"がある式内社〉
酒屋神社(さかや/さけや じんじゃ)は 佐牙神社とともに酒造りに縁ある式内社で 伝承には 神功皇后が三韓遠征の際 神社背後の山に酒壺を三個安置して出立 帰国後その霊験に感謝し創建 皇后が朝鮮より持ち帰った“九山八海の石”が今もここにあると伝わる 又 別説では中臣酒屋連が来往して 酒造りを伝え 祖神を祀ったとも伝わる
-

酒垂神社(豊岡市法花寺字長楽寺)〈延喜式内社〉
酒垂神社(さかたる/さかたれ じんじゃ)は 社伝は 白鳳3年(675)当地の郡司 物部韓国連久々比命が贄田(神田)に酒造所を造り 酒解子神 大解子神 子解子神の酒造3神を祀って神酒を醸造し 祖神に供えて五穀豊穣を祈願したのが創祀と云う 延喜式内社 但馬國 城崎郡 酒垂神社(さかたるの かみのやしろ)とされます
-

伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)〈式内論社3社〈大神神社・物部神社・堀坂神社〉を合祀〉
伊勢寺神社(いせでらじんじゃ)は 寛正2年(1461)当村で疫病が流行し多くの村人が亡くなり 疫病鎮めの神として一志郡多気村の牛頭天王社を当地に勧請し高福大明神と称したのが始めと言う 明治41年(1908)式内社の論社3社〈大神神社・物部神社・堀坂神社〉を含む35社を合祀します 昭和5年(1930)伊勢寺神社と改称
-

重浪神社(豊岡市畑上字宮)〈推古天皇25年(617)の創建・延喜式内社〉
重浪神社(しきなみじんじゃ)は 社伝によると 天武天皇 白鳳3年(675)6月 久久比命が城崎郡司となり その父・楮主(かみつ)命を敷浪の丘に葬り祠を建てて祀ったとき 共に祭祀を受け 重浪神社と称したと云う 延喜式内社 但馬國 城崎郡 重浪神社(おもなみ かみのやしろ)であると伝わります
-

伊川谷惣社(神戸市西区伊川谷町上脇)〈延喜式内社 物部神社〉
伊川谷惣社(いかわだに そうしゃ)は 神功皇后が三韓征伐の帰途 明石川から伊川を船でのぼり ここで一休みして「大国主命をここに祀れ」と命じたのが創始であると伝わります 『国内鎮守大小明神社記』では 延喜式内社 播磨國 明石郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)としています
-

可美真手命神社(押部谷町細田)〈延喜式内社 物部神社〉
可美真手命神社(うましまでのみこと じんじゃ)は 成務天皇十九年(149)に創建されたと伝えられる 延喜式内社 播磨國 明石郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)とされ 又 天平勝宝六年(754)摂津国住吉大社の社家「津守連」が楯神・鉾神と共に住吉大神を勧請したと伝えられる押部谷 住吉神社 最初の鎮座地です
-

物部神社(津市新家町)〈山辺の行宮〉〈延喜式内社〉
物部神社(もののべじんじゃ)は 古代この地方を支配した物部氏の一族 新家氏の氏神とされます 寛保元年(1741)の洪水により 古記録等が流失し創立当時の確かな記録はないが 当社は所替せず古来の地にあると云う 〈山辺の行宮〉の跡地ともされる 延喜式内社 伊勢國 壹志郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)とされます
-

大神社 旧鎮座地(松阪市深長町)〈延喜式内社の旧鎮座地〉
大神社 旧鎮座地(おおみわじんじゃ きゅうちんざち)は 明治四十一年(1908)高福神社〈現 伊勢寺神社〉に合祀された 延喜式内社 伊勢國 飯高郡 大神社(おほみわの かみのやしろ)の旧跡地です 現在は地域の鎮守の森のような存在で かつて境内にあった泉は 近隣の田畑を潤し 松坂城主の茶の湯にも使用されたと云う
-

久々比神社(豊岡市下宮字谷口)〈コウノトリの伝説or物部氏の伝承〉
久々比神社(くくひじんじゃ)は コウノトリが棲む地を「久々比(くくひ)」と呼び 社を建て木の神 久々遅命(くくのちのみこと)をお祀りして 始まったと云い 又 一説『国司文書 但馬故事記』には 物部韓國連 鵠(くくひ)〈久々比命〉を祀るとします 延喜式内社 但馬國 城崎郡 久久比神社(くくひの かみのやしろ)です
-

韓國神社(豊岡市城崎町飯谷)〈延喜式内社 物部神社〉
韓國神社(からくにじんじゃ)は 第25代 武烈天皇の命を受け 物部眞鳥(もののべのまとり)が 韓國へ派遣された後 但馬の楽々浦に着き 都へ報告に上った その功績により 韓國連を賜わり 物部韓國連眞鳥と称し その子・墾麿(こま)は 城崎郡司に任命され その孫・物部韓國連 鵠(くくひ)が創建した物部神社とされます
-

高牟神社(名古屋市名東区高針)〈『延喜式』高牟神社〉
高牟神社(たかむじんじゃ)は 元々は尾張物部氏の武器庫であり 高牟(たかむ)とは 古代の武器゛鉾゛の美称とされます 高針村の産土神として 江戸時代には應神天皇を祀り八幡社と称していました 昭和26年(1951)高牟神社と改称されました 延喜式内社 尾張國 愛智郡 高牟神社(たかむの かみのやしろ)の論社です