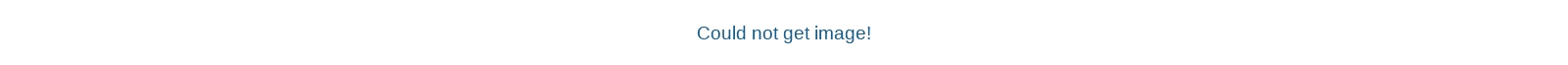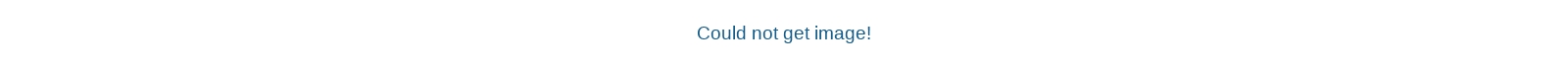延喜式神名帳
-

淡路国 式内社 13座(大2座・小11座)について
淡路国(あわじのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 淡路国 13座(大2座・小11座)の神社です 『古事記』『日本書紀』の記紀神話”国産み神話”によれば 日本列島で最初に生まれた島とされます
-

天利劔神社〈氣比神宮境内〉(敦賀市曙町)
天利劔神社(あめのとつるぎじんじゃ)は 祭神の天利劔大神が氣比大神の御子神であると『続日本後紀』承和7年(840)9月13日(乙酉)の条に「奉授 越前國 從二位勳一等 氣比大神之御子 无位 天利劔神 天比女若御子神 天伊佐奈彦神 並從五位下」と記される由緒格式ある古社です
-

安藝国 式内社 3座(並大)について
安藝国(あきのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 安藝国 3座(並大)の神社です
-

丹波國 式内社 71座(大5座・小66座)について
丹波国(たんばのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 丹波国には 式内社 71座(大5座・小66座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています
-

天伊弉奈姫神社〈氣比神宮境内〉(敦賀市曙町)
天伊弉奈姫神社(あめのいざなひめじんじゃ)は 祭神の天比女若御子大神が 氣比大神の御子神であると『続日本後紀』承和7年(840)9月13日(乙酉)の条に「奉授 越前國 從二位勳一等 氣比大神之御子 无位 天利劔神 天比女若御子神 天伊佐奈彦神 並從五位下」と記される由緒格式ある古社です
-

長門国 式内社 5座(大3座・小2座)について
長門国(ながとのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 長門国 5座(大3座・小2座)の神社です
-

周防国(すおうのくに) 延喜式内社 10座(並小)について
周防国(すおうのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 周防国の官社のことで 10座(並小)゛周防国には 10座(並小)゛熊毛郡2座・佐婆郡6座・吉敷郡1・都濃郡1座゛の神が坐しま゛の神が坐します
-

大神下前神社〈氣比神宮境内〉(敦賀市曙町)
大神下前神社(おおみわしもさきじんじゃ)は 氣比大神四守護神の北方鎮守社で元は北東の天筒山山麓の宮内村(現・敦賀市金ケ崎町)に境外末社として鎮座していた 明治四十四年(1911)鉄道敷設に伴って現在の地に遷座 稲荷神社 金刀比羅神社を合祀しました
-

備前国 式内社 26座(大1座・小25座)について
備前国(びぜんのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 備前国には 26座(大1座・小25座)の神々が坐します 現在の論社について掲載しています
-

美作国 式内社 11座(大1座・小10座)について
美作国(みまさかのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 美作国には 11座(大1座・小10座)の神々が坐します 現在の論社についても記しています
-

播磨国 式内社 50座(大7座・小43座)について
播磨国(はりまのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 播磨国 50座(大7座・小43座)の神社です 播磨国は 和銅6年(713) の詔によって『播磨国風土記』が編纂されていますので 7世紀には成立したとされています
-

佐渡國(さどのくに)の 式内社 9座(並小)について
佐渡国(さどのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社の一覧表です 佐渡国には 9座(並小)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています
-

越中國 式内社 34座(大1座・小33座)について
越中国(えっちゅうのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 越中国には 34座(大1座・小33座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています
-

能登國(のとのくに)の 式内社 43座(大1座・小42座)について
能登国(のとのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 能登国には 43座(大1座・小42座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています
-

森神社(天理市森本町)
森神社(もりじんじゃ)は 『延喜式神名帳927 AD.』所載の式内社 京中 左京二条坐神 太詔戸命神(ふとのとの みことの かみ)(大月次相嘗新嘗)の旧鎮座地とも 大和国 添上郡 太祝詞神社(大月次新嘗)(ふとのとの かみのやしろ)であるともされます
-

越前國 式内社 126座(大8座・小118座)について
越前国(えちぜんのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 越前国には 126座(大8座・小118座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています
-

肥後国 式内社 4座(大1座・小3座)について
肥後国(ひごのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 肥後国 4座(大1座・小3座)の神社です
-

国造神社(阿蘇市一の宮町手野)
国造神社(こくぞうじんじゃ)は 阿蘇神社の本宮ともされ その北方にあるので北宮と云う 第十代 崇神天皇の18年(紀元581)初代 阿蘇国造の速瓶玉命(はやみかたまのみこと)を その御子 惟人命(彦御子神)が勅により 阿蘇国造の神として 御居住の地(現在地)に鎮祭したのが創建と伝わります
-

陸奥國 式内社 100座(大15座・小85座)について
陸奥国(むつのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 陸奥国には 100座(大15座・小85座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています
-

上野國 式内社 12座(大3座・小9座)について
上野国(かみつけのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 上野国には 12座(大3座・小9座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています