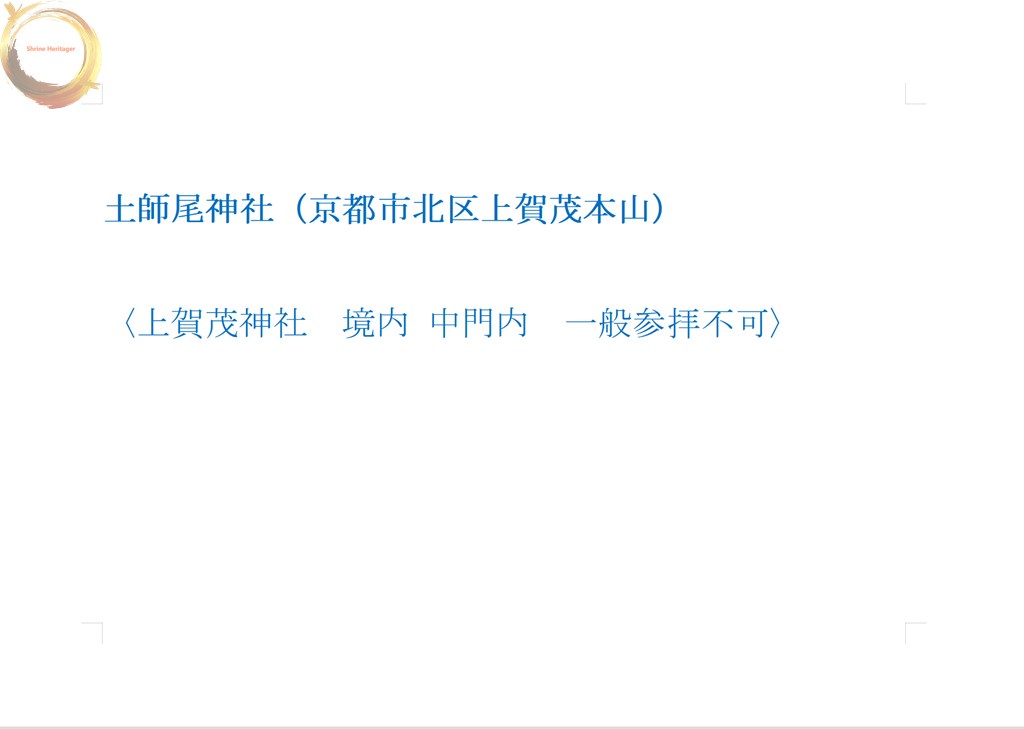延喜式神名帳
-

天一神社(佐用郡佐用町東徳久)〈播磨國風土記・六国史・延喜式に所載の社〉
天一神社(てんいちじんじゃ)は 社伝には゛今より約二千年前(彌生時代)に創立 日本でも最古の神社で寶剣(銅剣)が御神體なるは天智記に「安置御宅」゛と記され 『六国史』天安元年(857)天一神に從五位下が奉授 その7日後に官社に列すと記され 『延喜式』播磨國 佐用郡 天一神玉神社(あめひとつかんだまの かみのやしろ)です
-

佐用都比賣神社(佐用郡佐用町本位田甲)〈播磨國風土記・六国史・延喜式に所載の社〉
佐用都比賣神社(さよつひめじんじゃ)は 『播磨國風土記(713年)』讃容郡(さよのこおり)の条に 神代の神話として 神の名を贊用都比賣命(さよつひめのみこと)と名付けたとあり 『六国史』に嘉祥2年(849)官社に列し 『延喜式』に播磨國 佐用郡 佐用都比賣神社(さよつひめの かみのやしろ)とある 格式高い由緒を持ちます
-

乎疑原神社(加西市繁昌町)〈播磨國 河合郷加東・加西三十五箇村の総社〉
乎疑原神社(おぎはらじんじゃ)は 『播磨國風土記』゛揖保郡 萩原里(はりはら/をきはら のさと)゛の条に 鎮座地゛乎疑原(をきはら)゛の名付け由縁が記される古社で 加東・加西三十五箇村の総社として例祭には 国家より幣帛が供進された 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 乎疑原神社(をきはらの かみのやしろ)です
-

乎疑原神社(加西市豊倉町)〈延喜式内社 乎疑原神社(をきはらの かみのやしろ)〉
乎疑原神社(おぎはらじんじゃ)は 『國内鎭守大小明神社記』には゛荻原明神゛と載り゛萩原(をきはら)゛とも書きました 鎮座地゛乎疑原(をきはら)゛の名付け由縁は『播磨國風土記』゛揖保郡 萩原里(はりはら/をきはら のさと)゛の条に記されます 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 乎疑原神社(をきはらの かみのやしろ)の論社です
-

大神宮(京都市左京区静市市原町)〈岡本郷の産土神〉
大神宮社(だいじんぐうしゃ)は 鎮座地の市原はかつて「岡本郷」と呼ばれ その産土神でした 延喜式内社 山城國 愛宕郡 鴨岡本(かもをかもとの)神社について 伝承には ゛京郡府式内考證に 當社或は市原村の産神なりと云ひ 正保二年(1645)上申の書中に 山城國愛宕郡岡本郷市原村とあるを證としたる゛とあり論社となっています
-

嚴島神社(京都市左京区静市市原町)〈粟穂辨財天社(あはほのべんざてんのやしろ)〉
厳島神社(いつくしまじんじゃ)は 口伝に「老人の霊夢に 辨財天のお告げがあり 六寸の白蛇 粟の穗(あはのほ)に坐せり これを祀り 永享二年(1430)粟穂御前の鎮座」と伝え 江戸時代゛粟穂辨財天社(あはほのべんざてんのやしろ)゛と呼び 辨天祠を岡本堂の跡と考え 式内社 鴨岡本(かもをかもとの)神社の論社となっています
-

幸神社(京都市北区上賀茂岡本町)〈式内社 鴨岡太神社の旧社地〉
幸神社(さいじんじゃ)は 鎮座の年代は不詳ですが 口碑には 大田神社とともに 賀茂に於ける最古の社とも伝わり 古来から ゛神坂山(こうさかやま)゛を祀る社と伝わります〈上賀茂神社の御神体山は神山〉 延喜式内社 山城國 愛宕郡 鴨岡太〈鴨岡本〉神社(かもをかもとの かみのやしろ)の旧社地と云い伝わります
-

賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)の境内・境外の摂社・末社について
賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)の境内・境外は 境内の糺(ただす)の森は 鴨川と高野川の合流する三角州に山背盆地の植生を残す貴重な森林でその美しさは古くから物語や詩歌にうたわれます 多くの摂社・末社が祀られていますので その詳細について 現地の案内板を中心に見て行きます
-

出雲井於神社〈比良木大明神〉(京都市左京区下鴨泉川町)〈賀茂御祖神社 境内〉
出雲井於神社(いずもいのへのじんじゃ)は 式内社 山城國 愛岩郡 出雲井於神社(いつものゐのうへの かみのやしろ)であり 出雲郷の総社が「井於〈川=鴨川の辺〉」に鎮座する意味があります 又 厄年の御祈願で神社の周りに御献木すると ことごとく柊の葉の様にギザギザになり お願い事が叶うと云い 比良木社(柊社)とも呼ばれます
-

由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)〈都の北方鎮護の社〉
由岐神社(ゆきじんじゃ)は 天慶年間〈938~947年〉世情不安となった時 天下泰平と万民幸福を祈念し 朱雀天皇が勅により 元は 宮中〈京都御所〉に祀られていた由岐大明神〈大己貴命・少彦名命〉を 都の北方にあたる鞍馬山の地に遷宮をして 鞍馬寺の鎮守社とし 都の北方鎮護を仰せつけられたのが始まりです
-

末刀岩上神社(京都市左京区松ケ崎林山)〈延喜式内社 末刀神社〉
末刀岩上神社 (まといわがみじんじゃ)は 江戸時代までは社殿がなく 御神体゛大岩゛を磐座(いわくら)として 古代からの自然崇拝が今に続きます 桜井水〈涸れた事のない泉〉が下鴨神社へ流れる泉川の源流とされ 江戸時代に 下鴨神社の摂社 末刀社を名乗り 式内社 山城國 愛宕郡 末刀神社(まとの かみのやしろ)の論社となります
-

愛宕社・稲荷社(京都市左京区下鴨泉川町)〈下鴨神社 境内〉
愛宕社(おたぎのやしろ)賀茂斎院御所の守護神〉・稲荷社 忌子女庁屋の守護神〉の両社は 文明の乱で焼失以降 相殿として旧地に祀られます 又 末刀神が降臨したと伝わる゛水ごしらへ場゛と云う岩〈下鴨神社本殿の傍〉の祭祀が継承された愛宕社は 延喜式内社 山城國 愛宕郡 末刀神社(まとの かみのやしろ)の論社となっています
-

御蔭神社(京都府京都市左京区上高野東山)〈下鴨神社 境外摂社〉
御蔭神社(みかげじんじゃ)は 太古 賀茂の大神が降臨された所〈御生山(みあれやま)〉と所伝があり 現在でも 葵祭に先立って 祭神を降臨地である御蔭山から賀茂社へ迎える御生(みあれ)神事が行われています 綏靖天皇の御代(BC581)に創建起源とされ 二つの式内社〈①出雲髙野神社②小野神社二座 鍬靫〉の論社でもあります
-

猿田彦神社(京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊前町)〈平安京遷都を託宣せる神〉
猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)は 桓武天皇が この神の託宣により平安遷都を決意され 延暦12年(793)勅願によって社殿を造営と伝えます かつての広大な境内も 応仁の乱以後 度々火災に遭い悉く焼失 寛政5年(1793)現在地に遷座 延喜式内社 山城國 愛岩郡 出雲髙野神社(いつもの たかのの かみのやしろ)の論社です
-

上御靈神社(京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町)
上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)は 平安時代 御霊の祟りを恐れ 貞観5年(863)御霊会が修せられたのが 両御霊神社の創祀と云う 元は愛宕郡出雲郷の出雲路にある出雲氏の氏寺・上出雲寺に祀られた鎮守社 二つの式内社〈出雲井於神社(いつものゐのうへの かみのやしろ)出雲髙野神社(いつものたかののかみのやしろ)〉の論社です
-

下御靈神社(京都市中京区寺町通丸太町下ル下御霊前町)
下御靈神社(しもごりょうじんじゃ)は 平安時代 御霊の祟りを恐れ 貞観5年(863)御霊会が修せられたのが 両御霊神社の創祀と云う 元は愛宕郡出雲郷の出雲路にある出雲氏の氏寺・下出雲寺の御霊堂に祀られた鎮守社で 社家は代々出雲路家が司り 延喜式内社 愛岩郡 出雲井於神社(いつものゐのうへの かみのやしろ)ともされます
-

井上社〈御手洗社〉(京都市左京区下鴨泉川町)〈下鴨神社 境内社〉
井上社(いのうえのやしろ)は 賀茂斎院の御禊や解斎 関白賀茂詣の解除に参拝された御手洗社(みたらしのやしろ)で 旧鎮座地は 高野川と鴨川の合流地東岸〈文明二年(1470)焼亡〉文禄年間(1592~96)ここに再興〈井戸の井筒の上に祀られ井上社と呼ぶ〉式内社 出雲井於神社(いつものゐのうへの かみのやしろ)の論社です
-

三井神社(京都市左京区下鴨泉川町)〈下鴨神社の境内攝社〉
三井神社(みついじんじゃ)は 下鴨神社の本殿 すぐ左隣(西側)に鎮座する摂社です 奈良時代~平安時代この辺り一帯は蓼倉郷と呼ばれ 『山城國風土記』賀茂社の条「蓼倉里(たてくらのさと)三身社(みつみのやしろ)」とされます 延喜式内社 山城國 愛宕郡 三井神社(みゐの かみのやしろ)(名神大 月次 新嘗)の論社です
-

土師尾神社(京都市北区上賀茂本山)〈上賀茂神社 本殿廻廊内庭 一般参拝不可〉
土師尾神社(はじおじんじゃ)は 上賀茂神社の本殿廻廊の内庭に鎭座する小祠で 延喜式内社 山城國 愛宕郡 賀茂波爾神社(かものはにの かみのやしろ)の論社です 社名の゛土師(はじお)゛とは 上古に陵墓管理 土器や埴輪 (はにわ) の製作をした人を云い 鴨縣主と同祖 鴨建玉依彦命の後裔である「西泥土部」が祖神を祀った社です
-

賀茂波爾神社〈赤ノ宮〉(京都市左京区高野上竹屋町)〈下鴨神社 境外摂社〉
賀茂波爾神社(かもはにじんじゃ)は 江戸時代には゛赤ノ宮・赤宮稲荷大明神゛と呼ばれました 明治政府の指令により 近世に頽廃した 延喜式内社 賀茂波尓神社(かもはにの かみのやしろ)であるとされ改号したものです 赤ノ宮と呼ばれたのは 稲荷社の社殿が朱色の為 とも 土器の生産原料の赤土〈埴土〉に因んだとも云われます