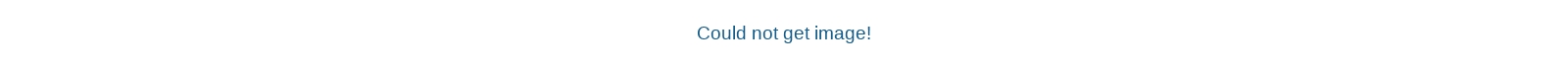岩手県
-

儛草神社(一関市舞川大平)〈『文徳實録』儛草神『延喜式』儛草神社〉
儛草神社(まいくさじんじゃ)は 社伝には大同2年(807)坂上田村麿によって創建と云う 又 養老二年(718)白山妙理権現が創建とも云う 六国史『文徳實録』仁寿二年(852)「儛草神」の神として神階の奉授が記される 延喜式内社 陸奥國 磐井郡 儛草神社(まひくさの かみのやしろ)とされる由緒ある古社です
-

鎭岡神社(奥州市江刺岩谷堂字五位塚)〈『延喜式』鎭岡神社〉
鎭岡神社(しづめがおか じんじゃ)は 称徳天皇(764~)の御代に勧請『安永風土記(1772~81年)』とある延喜式内社 陸奥國 江刺郡 鎭岡神社(しつめをかの かみのやしろ)です 又 天明5年(1784)国学者 菅江眞澄が「かしこしな あらふるとても ぬさとらば こころしつめの 岡の神籬(ひもろぎ)」と歌を詠みました
-

尾崎神社 本殿(大船渡市赤崎町鳥沢)〈『文徳實録』理訓許段神〉
尾崎神社 本殿(おさきじんじゃ ほんでん)は 真北方向の蛸ノ浦漁港に鎮座する尾崎神社 遥拝殿の本殿になります 社伝によれば 人皇第五十代 桓武天皇の御宇 延暦二年(783)に創立 『文徳實録』理訓許段神 延喜式内社 陸奥國 氣仙郡 理訓許段神社(りくこたの かみのやしろ)であると伝えています
-

尾崎神社 遥拝殿(大船渡市赤崎町鳥沢)〈『文徳實録』理訓許段神〉
尾崎神社 遥拝殿(おさきじんじゃ ようはいでん)は 後水尾天皇の御宇 寛永二年(1625)類焼に罹り古文書 宝物悉く焼失 由緒沿革の要領不祥ですが 延喜式内社 陸奥國 氣仙郡(けせんの こおり)3座(小)の一つ 理訓許段神社(りくこたの かみのやしろ)と伝えています こちらは遥拝殿で後方の山上に本殿が祀られています
-

冰上神社(陸前高田市)〈『文徳實録』登奈孝志神・衣太手神・理訓許段神〉
冰上神社(ひかみじんじゃ)は 元々冰上山の麓に『延喜式』所載の氣仙郡三座〈理訓許段神社(りくこたの かみのやしろ)・登奈孝志神社(となこしの かみのやしろ)・衣太手神社(きぬたての かみのやしろ)〉があり 中世 修験道の山岳信仰により 冰上山の山頂に三宮を集め氷上三社と総称され 当社はその里宮にあたります
-

陸奥國 式内社 100座(大15座・小85座)について
陸奥国(むつのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 陸奥国には 100座(大15座・小85座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています
-

駒形神社 里宮(陸中国一之宮)
駒形神社 里宮(こまがたじんじゃ さとみや)は 江戸時代(1603年 ~1700年頃)に仙台藩側から駒ヶ岳山頂の奥宮に向かう参拝路口にあたる「金ヶ崎の里宮」になります 明治4年(1871)に 山頂の「奥宮」が 国幣小社に列する際に 奥宮・里宮とも参拝時の交通が不便であるので 当時の水沢県県庁に近い水沢の鹽竈神社の本殿が仮遥拝所とされました それが現在の駒形神社「本社」となります この「奥宮」と「本社」の中間なので「中宮」とも呼ばれています
-

駒形神社 本社(陸中一宮)
駒形神社 本社(こまがたじんじゃ ほんしゃ)は 「陸中国一之宮」とされていて 駒ヶ岳山頂に「奥宮」が鎮座します 古代には 付近一帯が軍馬の産地であったと考えられていて 御祭神「駒形神」は「馬の守護神」ともされています 馬頭観音や大日如来と神仏習合して 東日本の各地に勧請されて 広く信仰されていきます