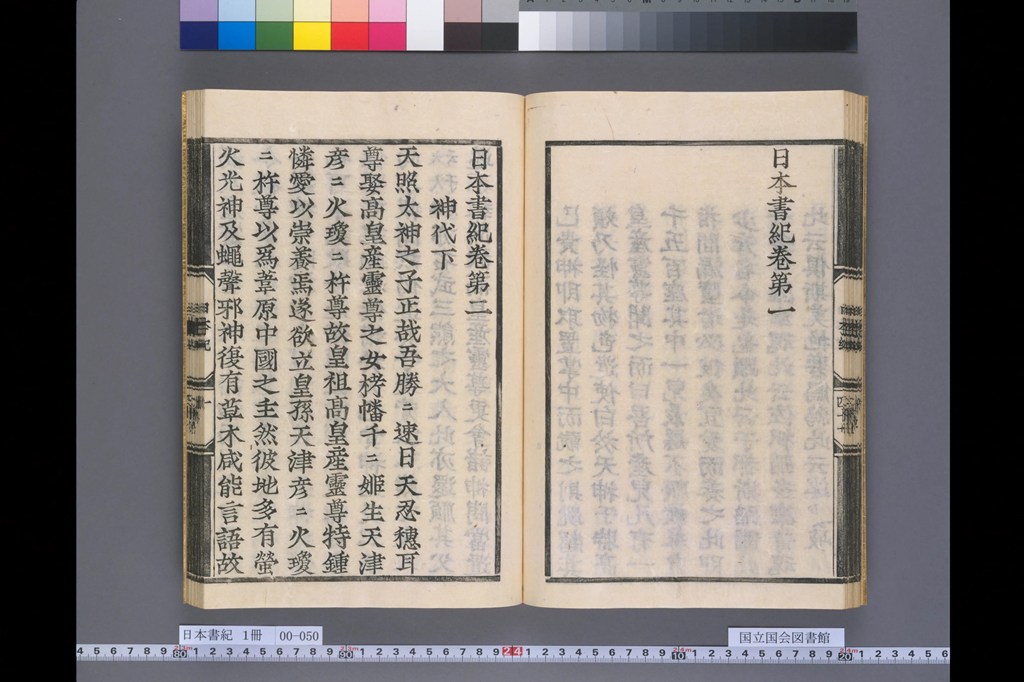-

廣幡神社(菰野町菰野)〈式内論社 江田神社(江田)明治41年(1908)合祀〉
廣幡神社(ひろはたじんじゃ)は 寛永七年(1630)菰野藩初代藩主 土方雄氏公が京都の石清水八幡宮より城の鎮守として勧請 明治になり神社合祀令により近隣の神社が合祀されました 明治41年には式内論社 江田神社(江田)を合祀して 延喜式内社 伊勢國 三重郡 江田神社(えたの かみのやしろ)の論社となっています
-

鵜森神社(四日市市鵜の森)〈『延喜式』江田神社〉
鵜森神社(うのもりじんじゃ)は 鎮座地は濱田城跡にあり 創建年代は定かではないが 文明(1469~87年)には濱田城主 依家の崇敬した社であった 一説には 元は江田神社と称していたとされ延喜式内社 伊勢國 三重郡 江田神社(えたの かみのやしろ)の論社となっています
-

江田神社(四日市市西坂部町)〈『延喜式』江田神社〉
江田神社(えだじんじゃ)は 祭神は日本武尊の弟君 五十功彦命 古くは奥宮 中宮 下宮があったが 天正3年(1575)織田信長配下の兵火によりすべてを焼失し 下宮〈現在地〉に遷座 明治41年(1908)に坂部町地内のすべての神社が合祀されました 延喜式内社 伊勢國 三重郡 江田神社(えたの かみのやしろ)の論社です
-

江田神社(宮崎市阿波岐原町)〈『續日本後紀・三代實録』江田神『延喜式』江田神社〉
江田神社(えだじんじゃ)は 社伝に「太古の御創建 この地一帯は古来 所謂 日向の橘の小戸の阿波岐原として 伊邪那岐の大神禊祓の霊跡と伝承されて 縁起最も極めて深き社ならむ」とあります 六国史『續日本後紀』『三代實録』江田神とあり 『延喜式』日向國 宮崎郡 江田神社(えたの かみのやしろ)とされます
-

邇々杵尊(ににぎのみこと)木花之開耶姫(このはなさくやひめ)『記紀神話』の伝承
『記紀神話(ききしんわ)』「天孫降臨(てんそんこうりん)の段」には 邇々杵尊(ににぎのみこと)が 笠紗御前(かささのみさき)で 大山津見神(おほやまつみのかみ)の女(むすめ)木花之佐久夜毘賣(このはなさくやひめ)と出逢い 結婚 妊娠 出産についての伝承が語られています その舞台は日向國(現 宮崎県)です
-

西都原古墳群〈石貫神社〉『記紀神話』邇々杵尊 木花之開耶姫の伝承地
西都原古墳群(さいとばるこふんぐん)は 邇々杵尊 木花之開耶姫 大山津見神の墳墓とされる古墳がある『記紀神話』の伝承地です その他 姫が出産の時 周囲に火をかけたとされる産屋「無戸室」・産湯としたとする「兒湯の池」もあり 又 鬼の伝説を持つ大山津見神を祀る石貫神社(いしぬきじんじゃ)もあります
-

都萬神社(西都市大字妻)〈『續日本後紀』妻神『三代實録』都萬神『延喜式』都萬神社〉
都萬神社(つまじんじゃ)は 社傳に云く「景行天皇 日向國 土蜘蛛を征し給ふ時、兒湯縣に行幸 当社勅願し給ひしことを傳ふ 以てその太古の創建なるを知るべし」とあります 『續日本後紀 妻神』『三代實録 都萬神』『延喜式』に日向國 兒湯郡 都萬神社(つまの かみのやしろ)と記載のある由緒ある古社です
-

羊神社(名古屋市北区辻町)〈『延喜式』羊神社〉
羊神社(ひつじじんじゃ)は 群馬の多胡郡の領主 羊太夫が奈良の都へ上る時 この地(現辻町)に立ち寄った屋敷があり 土地の人々が平和に暮らせるように火の神を祀り 羊神社と名付けられたと伝えら「辻町」は「ひつじ」から「ひ」をとったとも云う 延喜式内社 尾張國 山田郡 羊神社(ひつしの かみのやしろ)の論社です
-

高牟神社(名古屋市守山区瀬古東)〈『延喜式』髙牟神社・羊神社〉
高牟神社(たかむじんじゃ)は 創建は社記に「養老元年(717)鎮座 高見と云ふ名稱を賜ふ」云々と見え 『本国帳』従3位高牟天神・『尾張本国内神明帳』従3位上高見天神とする古社で 延喜式内社 尾張國 春日部郡 髙牟神社(たかむの かみのやしろ)と云う 又一説に延喜式内社 山田郡 羊神社(ひつしの かみのやしろ)とも云う
-

勝川天神社(春日井市勝川町)〈『延喜式』髙牟神社〉
勝川天神社(かちがわてんじんしゃ)は 正和二年(1313)無盡禅師によって創建と伝え もとは高山という所にあったが 後世 今の地に移し 神仏混淆の時代には地蔵寺が祭祀を掌ったと云う 又『又張神名帳集説訂考』には従三位 高牟天神すなわち 延喜式内社 尾張國 春日部郡 髙牟神社(たかむの かみのやしろ)とする説があります
-

五社神社(春日井市玉野町)〈『延喜式』髙牟神社〉
五社神社(ごしゃじんじゃ)は 社伝は明らかではありませんが 『張州府志』に「五社祠 玉野村に在り 明神、神明、天神、八幡、多度、の五社を祀り 永享元巳酉年(1429)村民之を建てる」とあります 一説には 延喜式内社 尾張國 春日部郡 髙牟神社(たかむの かみのやしろ)とする説があります
-

高田寺白山社(北名古屋市高田寺)〈『延喜式』髙牟神社〉
白山社(はくさんしゃ)は 創建年代は不祥ですが 社伝に「延喜神名式 髙牟天神」即ち 延喜式内社 尾張國 春日部郡 髙牟神社(たかむの かみのやしろ)であると伝わっています 又『尾張国内神名帳』に載る「従三位 高牟天神」とも「従三位 小高薗天神」とも云われます
-

松原神社(春日井市東山町)〈『延喜式』髙牟神社〉
松原神社(まつばらじんじゃ)は 元明天皇の御代 和銅四年(711)創建と伝え 社地の辺りは古来地名を高牟(たかむ)と呼び 社名も古くから高牟神社と号し 延喜式内社 尾張國 春日部郡 髙牟神社(たかむの かみのやしろ)とされます 中世に稲荷信仰が普及して合祀され 江戸時代の棟札には高牟稲荷大明神と記したものがあります
-

八所神社(豊山町豊場木戸)〈『延喜式』物部神社・髙牟神社〉
八所社(はっしょしゃ)は 物部氏一族により開拓されたこの地に 物部氏神〔大和の石上神宮より分神を勧請〕を斎き祀った社とされ 社伝に「和銅二年(709)創建 元 物部神社(八所太明神)と稱した」とあり延喜式内社 尾張國 春日部郡 物部神社(もののへのかみのやしろ)であると云う 又 髙牟神社(たかむのかみのやしろ)とも云う
-

味美白山神社(春日井市二子町)〈『延喜式』物部神社を合祀〉
味美白山神社(あじよし はくさんじんじゃ)は 元は今より南の白山藪(味鋺字堂前898)に鎮座したが 萬治二年(1659)現在地(白山神社古墳の墳丘上)に遷座 同時に 二子山古墳の墳丘にあった物部天神〈式内論社〉を合祀し建立されたと云う 延喜式内社 尾張國 春日部郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)の論社です
-

諸大明神社(春日井市松本町)〈『延喜式』物部神社〉
諸大明神社(もろだいみょうじんじゃ)は 一説には養老年間(717~724年)又は養老2年(718)の創建とされる古社で『尾張神名帳』などは春日部郡 従三位 松原天神とします 又 一説に延喜式内社 尾張國 春日部郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)ともされます
-

古代豪族〈武力と祭祀を担う〉物部氏 と「延喜式内社 物部神社」について
物部氏(もののべうじ)は 太古の大和朝廷で 神道を奉じ軍事を司る氏族として「八十物部(やそのもののべ)」と云われ 絶大な勢力を保持していました その後 神道を奉じる物部氏の宗家〈物部守屋大連〉は 仏教を信奉する蘇我氏〈蘇我馬子 大臣〉と用命天皇2年(587)戦い敗れ 物部氏は徐々に衰退をして行く事になります
-

三明神社(小牧市林北)〈『延喜式』非多神社〉
三明神社(さんめいじんじゃ)は 承和8年(841)創建 戦国時代までは大縣神社の摂社と社伝に云う 又 江戸時代の編纂物『尾張志』『尾張地名考』『尾張名所圖會』等は「林村字平野と云所に稗田天神 又 樋田天神ありしが今廃して三明神相殿」と 延喜式内社 尾張國 春日部郡 非多神社(ひたの かみのやしろ)てあると記しています
-

六所神社(名古屋市西区比良)〈『延喜式』非多神社・乎江神社〉
六所神社(ろくしょじんじゃ)は 創建年代は不祥 本殿の両脇にある2つの境内社(・非多神社・ 大江神社)が式内論社とされていて〈①延喜式内社 尾張國 春日部郡 非多神社(ひたの かみのやしろ) ②延喜式内社 尾張國 春日部郡 乎江神社(をえの かみのやしろ)〉 二つの式内社の論社となっています
-

八幡神社(瀬戸市水北町)〈『延喜式』乎江神社〉
八幡神社(はちまんじんじゃ)は 創建年代は不祥 延宝四年(1676)尾張藩主乙世光友の再建と伝わり 『尾張志』に「上水野村の八幡社は境内ひろく 其地を字江の山日呼ひ 東に隣れる藥師堂法松院の山號を上(ウヘ)之山といへるも宇江の轉したる由」と延喜式内社 尾張國 春日部郡 乎江神社(をえの かみのやしろ)の論社としています